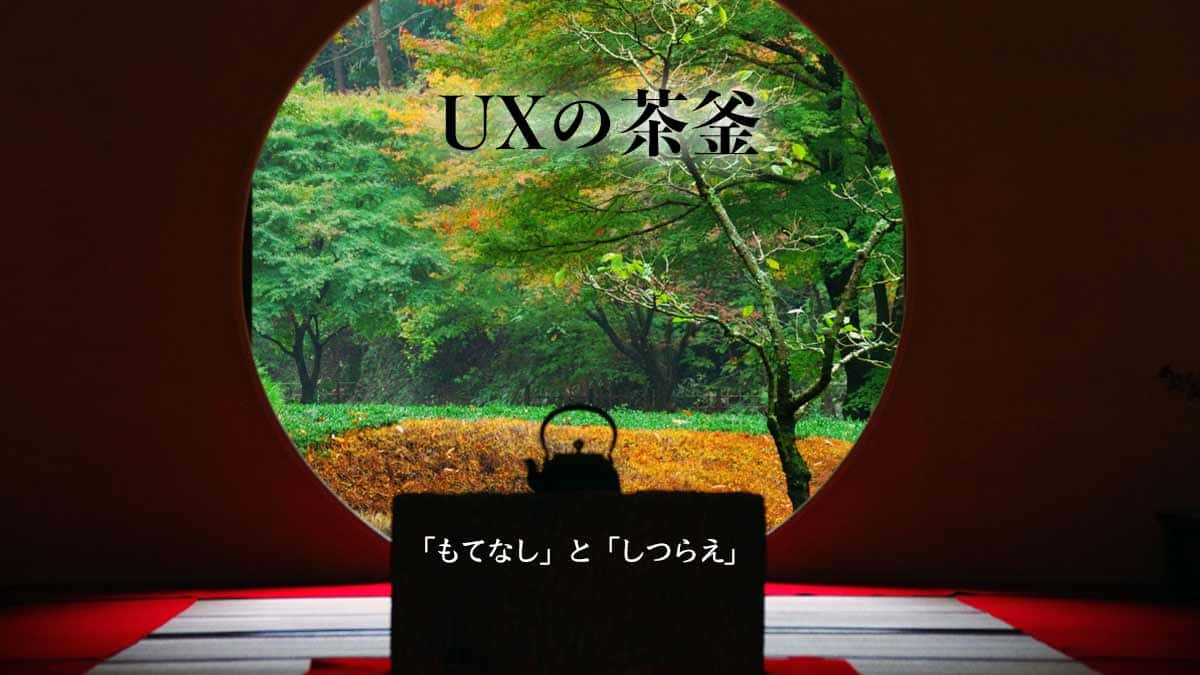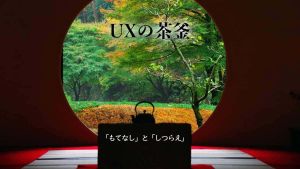デジタル時代において、ユーザーエクスペリエンス(UX)の設計は、単なる機能や利便性を超え、心に響く体験の創出が求められています。
約430年前、安土桃山時代の千利休が茶道で表現した「もてなし」と「しつらえ」の美学は、現代のUX(ユーザー体験)設計において驚くほど本質的な示唆を与えてくれます。禅の精神を基盤とする茶道では、体験そのものが教えであり、身体で覚える智慧として受け継がれてきました。
シリーズ2回目となる今回は、茶道の「もてなし」と「しつらえ」から学ぶ、真の一体感を生み出すUX設計の秘訣を探求します。
デジタル時代の関係性構築において、この古来の智慧がどのように現代のビジネスに影響をあたえるのか、その核心に迫っていきます。
禅の教えと茶の湯:現代UXデザインの源流を探る
茶の湯の歴史背景
奈良時代に遣唐使により茶葉が運び込まれて以来、当初は薬用として珍重されていたお茶も、嗜好性が強まり次第に茶の湯の作法や文化として黎明期を迎えて行きます。鎌倉時代に禅僧の栄西が中国の宋(そう)より抹茶の茶種の種と喫茶法を持ち帰ってきました。その喫茶法が宋時代の禅宗が生み出した原型と言われています。
南方禅の宗派が道教の教義を大幅に取り入れて精緻な茶の礼法を作りあげた。僧侶たちは達磨の像の前に集まり、神聖な儀式の厳かな形式にのっとって一碗の茶を順に飲んだ。この禅の礼法こそがついには十五世紀日本において茶の湯を生み出すことになったのだ。
岡倉 天心「新訳 茶の本」より
室町時代に貴族などの間で唐物の美術品を中心に愛でてる茶会から、簡素な環境で精神的な場を求める「侘び(わび)茶」を村田珠光(むらたじゅこう)が始め、その後、侘び茶の精神は大阪の境の商人、武野紹鴎(たけのじょうおう)により深められその弟子の千宗易(せんのそうえき、後の千利休)により「侘び茶」が大成していきました。
禅が「静寂無垢の世界」を理想とするならば、古来より日本の文化に根付く自然崇拝と融合して侘び茶の美意識や精神文化が無理なく生活の中に定着してきます。特に千利休により旧来の高価な唐物道具に傾倒する傾向から見立てなどにより、身の回りの日常品を応用すれば誰でも創意工夫することで茶を楽しむ様式に茶の湯を再定義しました。
この日本で熟成された言われる茶の湯のシステムに現代のユーザーエクスペリエンス設計(UXデザイン)に役立つヒントが隠されています。そのヒントを紐解いていきましょう。
茶道の美意識とUXデザイン:体験価値の原則
「利休七則」の一体感の重要性
茶道の精神を理解する上で、利休が弟子に説いたと言われる「利休七則」を紹介します。
茶は服のよきように
裏千家 今日庵HPより
炭は湯の沸くように
夏は涼しく、冬は暖かに
花は野にあるように
刻限は早めに
降らずとも雨の用意
相客(あいきゃく)にこころせよ
最初の「茶は服よきように」の解釈は、味わいだけでなく心をこめて点(た)てることで亭主と客との一体感の重要性を説いています。因みに「服(ふく)」とは、「一服する」の語源である茶を飲む行為を表します。
2番目の炭の扱いについては単にゆを湧かすための工夫や、形式的な作法を説いているのでなく、炭などモノの本質をよく見極めることの重要性を表しています。
3番目の季節感への気遣いと4番手の「花はのにあるように」における自然から与えられたいのちの尊ぶ気持ちはどちらも、目で読み込むだけでなく心で感じ取りその本質を理解し盛り込む(溶け込む)必要性を説いているとも解釈できるでしょう。
5番手は主と客がこころを開いて向かい合うために、ゆとりある時間を尊重する意味合いを説き、6番手の心がけは、どんなときにも適切で場に応じられる柔らかいこころを持つ必要性をたしなめています。
最後に述べられている「相客」については招いた客人同士、身分に関係なく互いを尊重しあう和のひとときの大切さを説いています。
至極あたりまえのことを実践する難しさがこの七則には込められています。更に表層と深層に気を遣いながらこころの目でものごとを捉える重要性もここでは語られていると感じ取れます。
現代のユーザーエクスペリエンス設計においては特にオンラインなど非対面の空間が中心となり、まさに目に見えない深層へこころを馳せることの重要性に茶道とUXの共通する部分があります。
茶の湯の精神である四規「和敬清寂」というコンセプト
更に茶道の精神を理解するうえで茶の湯の本質を捉えている四規「和敬清寂」という成句があります。この意味は、どのような人とも和みと敬いの世界と清らかなるこころもちで物事に動じない平常なる時を生み出していく大切さが各四文字に込められていると言われています。
七則の行動規範(スクリプト)に対して、四規は茶道の筋書き(コンセプト)とも言えるかと感じます。ここで七則の視点を振り返ると1番から6番までの主語は亭主から客人に対して、最後の七番手は客人同士の心得というのがどの文献でも一般的な解釈とされています。
最後の心得においても、招き入れている主が客人間における和を尊ぶための目配せや気遣いの重要性をも説いているのではないかと個人的には解釈しています。
それは茶の湯のコンセプトでもある「和敬清寂」の場を築くのはホスト側の役目でもあるが故です。ただ、茶の湯は亭主と客人が双方で生み出す一体感と考えるならば、この利休七則はそのどちらの視点(=主語)でも意味が通ずる教えとも解釈は出来ますので、とても奥の深いスクリプトであると感じます。
この茶の湯を表す「四規七則」は、茶を通じて人との交わりの重要性や目に見えない部分にも理解と共有をすることで一体となり命を分かち合うことを双方が悟る時空であると考えられます。
これは現代のユーザーエクスペリエンス設計において、企業と顧客の関係性における一体感の構築は、世界共通の真理といえます。
ユーザーエクスペリエンスを、迎える側(企業)と招かれる側(顧客)の関係性において一体感を構築する目的と再定義するならば、ブランドのストーリーやサービスが全ての接点において同一であり、その結果、双方に共感が芽生えて一体感(=ブランディング)が確立されます。
つまり、共感設計がユーザーエクスペリエンス(UX)という体験設計に重要な要素であるならば、茶道における具体的な共感発生要素でもある「もてなし」と「しつらえ」の精神とは何かを解説していきます。

「もてなし」と「しつらえ」のユーザーエクスペリエンス設計
「独服」の精神:自分をもてなす」ことから始まる真の対話力
茶道では、自分のために点てる「独服」を通じて自己と向き合い、己を知り客人をもてなす心を整えます。
他者との関係を云々する前に、まず自分自身としっかり向き合う、いわば「自分をもてなす」ことができなければ、他者の心情を察し、慮り、もてなすことはできません。だからこそ、人を「おもてなし」する前の独服、自分自身と向き合う機会を作るところに茶の湯の原点があり、これこそが禅と共通する部分ではないかと思うのです。
千宗屋 著『茶:利休と今をつなぐ』新潮新書より
この著書で語られている「『自分をもてなす』ことができなければ、他者の心情を察し、慮り、もてなすことはできません」の一文は、現代のユーザーエクスペリエンス設計(UX)においても重要な示唆が含まれています。つまり、自分も一人のユーザーとして提供する価値に満足できているのか向かい合うことの必要性を説いています。

ユーザー体験をデザイン(設計)するにあたり、自分たちが提供するサービスや商品に対して十分な愛情を持ち合わせて居るか、もしくは維持出来ているかを日頃から整えておくことで、心・技・体の三位一体のおもてなしに繋がると考えます。
■おもてなしの設計図:心技体フレームワーク:
- 心:思い遣り、気遣い、丁寧で感謝あるこころもち
- 技:心配りにおけるこころを伝える伝達技術や豊富な知識
- 体:目配り、手配り、身配りなどの表現伝達における動作や所作
五感に響く「しつらえ」:顧客の心を動かす総合演出の秘訣
「もてなし」が内面的要素なら、「しつらえ」は表層的な演出要素として、それに対して形にして伝える表層的な要素の「しつらえ」の演出が茶道の体験を更に深めていく材料になっています。
茶室に入る前に庭と一体になる露地(=路地)を通り四季や自然を感じながら世俗を浄化してにじり口を潜って茶室へ入ります。そして非日常的な狭い空間で床の間の花や掛け軸、茶器、一汁三菜の料理など亭主が準備した「しつらえ」に向き合い対話を楽しんでいきます。

亭主はそれぞれのしつらえに対する客人からの質問に、亭主の物語りを施していきます。それにより狭き囲いの茶室の体験は、茶を服みながら亭主と客人、そして個々の内面との対話による和みを堪能する時間が形成されていきます。
それは自分一人では成し得ない、人やものとの繋がりから生まれる一体感の悦びが茶の湯を引き立てていると言えるでしょう。※この状況を茶道では「一座建立」という成句で言い表します。
昨今のユーザー体験の重要性も、利用者における購入や利用時の瞬間の感情を整える事だけでなく、提供側のストーリーの伝達手段やそれぞれとの対話が生まれる仕組みのデザインを含め、「もてなし」のこころと「しつらえ」の準備・演出が重要なことは既に察することと思います。
今回、茶道の「もてなし」や「しつらえ」によるUX設計のポイントである「一体感」の醸成は、現代のブランディングやサービスデザインに大きな参考になると考えます。

またコロナ禍以降の非対面時代において、茶道の「もてなし」と「しつらえ」による一体感の醸成は、業界を問わずファン作りのヒントとなります。ポイントは、「もてなし」の心得を自覚し「しつらえ」の演出が細部までセットで提供されるところです。
おわりに
「もてなし」の心得とユーザー体験(UX)の共通項
私が茶道に触れたのは、高校の文化祭での茶会でした。「無料でお茶とお菓子が楽しめる」という軽い動機で足を運びましたが、そこには何か異質な空気が流れていました。精緻な所作に込められた意識、音のない時間の力、張りつめた静けさ。そうしたものが、静かに私の心に刻まれていきました。
その後、UXコンサルティングに携わる中で、あの体験がふたたび思い出される場面がありました。目に見えるスペックや操作性だけでは、ユーザーの記憶には残らない。むしろ、「気づかれない工夫」や「目に見えない配慮」こそが、心に触れる体験をつくっているのだと実感しました。
千利休の「利休七則」や「四規七則」は、一見平凡な言葉に見えますが、その背景には相手を思いやる深い洞察と、あたり前を徹底する強い信念があります。これは現代のUX設計にも通じる行動規範と言えるでしょう。
プロダクトやサービスは、単なる利便の提供にとどまらず、企業の姿勢や文化を映し出すものです。
私たちは今、即時性と効率が求められる時代に生きています。しかし、表層的な設計に流されず、なぜその体験を提供するのかという根本の問いに立ち返ることが、ますます重要になっています。「しつらえ」とは単なる装飾ではなく、関係性を整え、信頼を築くための枠組みです。その思想が、受け手の無意識に働きかけ、企業と顧客の間に深い「間」を生み出します。
顧客体験とは、本来、設計されるものではなく、組織の信念から滲み出るものです。貴社が設計しようとしているユーザー体験は、単なる快適さや機能性の提供にとどまるものではありません。それは、社会との関係性をどのように築き、自社の存在意義をいかに体現するかという、企業の根源的な問いに直結しています。
茶の湯における「もてなし」と「しつらえ」が、形式を超えて人の心を動かすように、UXの本質もまた、顧客の行動を超え、企業の信頼と文化を育てていくものです。
今、私たちが問うべきは、「どのように体験を整えるか」ではありません。問いの本質は、「いかにして、体験を通じて企業の思想を伝えていくのか」にあります。
その問いに向き合うことこそが、持続可能なブランド価値の礎となるのです。
- 表層と深層を意識しながら目に見えない部分とも向き合えるよう自身との対話から準備を進める
- もてなす側(企業)は、共感されるための心得と演出設計のセットで一体感を創出するユーザー体験構築を成す
- 自分一人では成し得ない「一体感」が、ユーザーとの共感を深め人やものを繋ぐ役割となる
参照情報
- 岡倉 天心「新訳 茶の本 ビギナーズ」KADOKAWA 2014年
- 千 宗屋「茶:利休と今をつなぐ」 2010年
X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を見逃すこと無く閲覧できます。