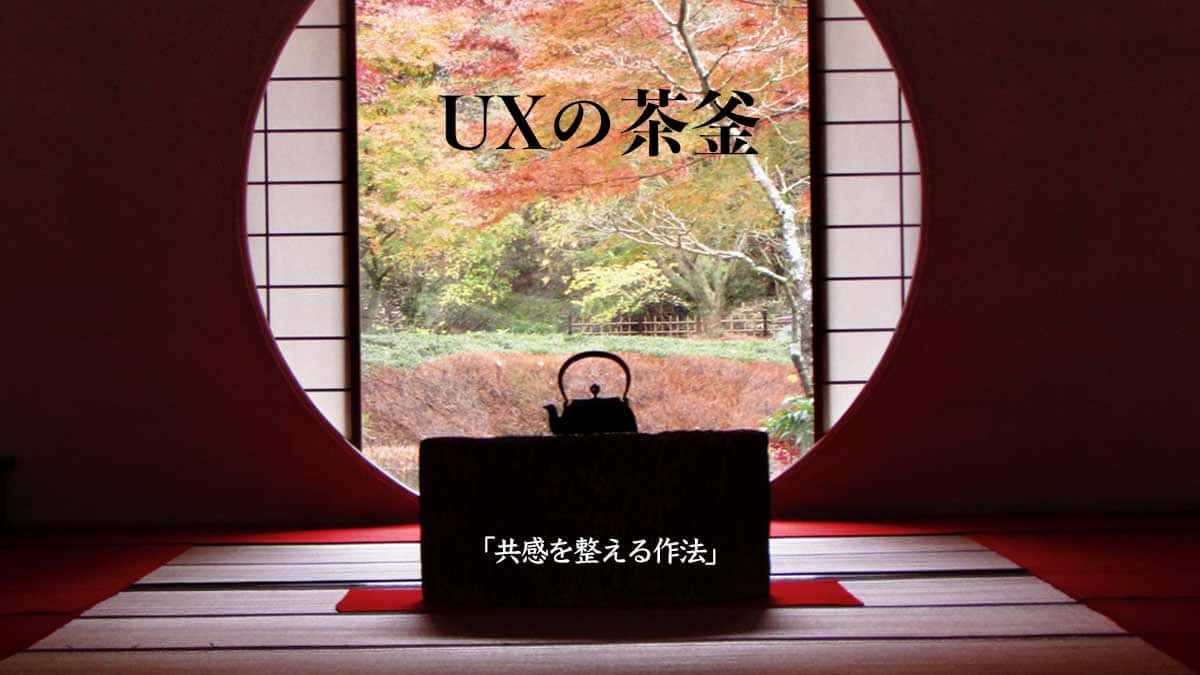UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、ユーザーが製品、サービス、システムを利用する際に感じる全体的な体験や感情を指す概念です。単なる機能性だけでなく、心理的、感情的、実用的な側面を包括的に評価します。
今回は、千利休の茶道の思想・哲学からUXを再考するシリーズ第1回目。UXにおける共感マップや関連の深いデザイン思考(デザインシンキング)の問題解決プロセスにおける、対象者を深く理解する「共感」という行為について考察します。
幼い頃、親から「相手の気持ちになって考えなさい」と周りを思いやる気持ちを諭された記憶はあるかと思います。この広義としての共感は、単に感情に寄り添い「同情」を表す感情移入の行為にとどまります。
デザイン思考では、ユーザー中心の課題解決手法として、共感、問題定義、アイデア発想、プロトタイピング、テストの5つのプロセスで構成されています。特に、ここでの「共感」とは、問題の本質を探るために、相手の視点で深く観察し、感情や行動を理解する活動です。
千利休の茶の湯の発想とシステムを参考に、UXデザインを構築するために必要な「共感力」を考えていきます。
千利休の茶道から学ぶUXデザインの本質
「にじり口」のユーザー体験設計
制限によって生まれる能動的な体験装置

茶室には、躙口(にじり口)と呼ばれる客用の小さな出入り口(左側の写真下部の四角い引き戸)があります。
これは、茶人・千利休が封建社会で戦国時代という主従関係が強い時代に、茶室の中は全ての人が平等であることを示すため、あえて入り口を低くし、刀などの装身具を外させ頭を下げなくてはならない仕組みでした。そのため、高さ約66cm x 幅約63cmほどの小さな入り口を茶室に設けたと言われています。
茶室の中では、自分というものを一度捨て、互いにひとりの人間として対峙するための仕掛けとして、空間の所作によって気付かせる究極のユーザー体験装置(UI:ユーザーインターフェース)です。これは、ユーザーがサービスや製品と相互作用する全ての接点を指す言葉でもあります。
また、デザイン思考における共感プロセスでは、思い込みを排除することが重要です。
偏見や自己中心的な視点は、対象者を深く理解する上で大きな障壁となります。対象者を観察し理解する際には、まずこれらの偏見を意識的に排除することが必要です。
具体的な方法として、一人ではなく数人で意見交換しながら進めることで客観的な視点を維持しやすい環境を築きます。更には、「ユーザーインタビュー」や「ユーザー調査」などの仮説を超えた現状の理解に努めます。
また、ユーザー像を擬人化した「ペルソナ」を設定し、その人物像の活動を時間と感情軸で表した「ジャーニーマップ」などの手法では客観的に問題発見を可視化し統一した共感イメージを醸成することで、課題解決におけるブレない方向性を確立する意図と役割があります。
- ペルソナとは何か
-
ペルソナとは、架空のユーザー像を具体化したものです。具体的な属性(年齢、職業、興味、悩みなど)を持たせた仮想的なユーザープロファイルのことです。その人物像の活動を時間と感情軸で表した『ジャーニーマップ』と組み合わせることで、製品やサービスの開発において、ユーザーの体験をより深く理解し、効果的な解決策を導き出します。
- ジャーニーマップの解説
-
ジャーニーマップとは、ユーザーが製品やサービスと関わる全プロセスにおける体験を時系列で可視化する分析ツール。各接点での感情や行動、思考を詳細に記述することで、ユーザーの本質的なニーズや課題を客観的に発見し、問題解決の切っ掛けを見出すための手法です。
「共感力」とは何か
UX設計を阻害する「共感力」不足の3大障壁
まず本質を理解する上で、デザイン思考のプロセスにおける共感を妨げる主なネガティブ要因から整理し、その後に全体構造を考えてみましょう。
- 1.周囲へ興味関心が低い
-
周りのひとや変化に関心が薄く無神経
- 2.自己顕示欲が強い
-
他人の話しを聴くよりも自分のことばかり話したがる
- 3.偏見の眼差し
-
思い込みや決めつけが強く、他人の意見に否定的発言が多い
会社組織や日常など、何処にでも居そうで特定の人物像を思い浮かべるかもしれません。仮にその様な方々が周りに居たとしても逆に「共感力」を整える良い機会に成り得るとも考えられます。
そもそもデザイン思考の「共感」とは先述した通り、対象者を深く理解し問題定義を進めるための行為です。勿論、上記3つのマイナス要因を自分自身に向けて、周りを観察して相手の気持ちを察し、話に耳を傾けたり、また、偏見を持たないよう意識することで「共感力」は日々の実践を通じて向上します。
これらネガティブ要因を意識しつつ、今度は共感を支えるポジティブな特徴を確認し、「共感」の輪郭を明確にしていきます。
UXデザインの共感力を高める3要素と実践方法
- 1.観察力
-
周囲に対して好奇心を持ち状況を受け入れる広い視野
- 2.想像力
-
相手の視点で物事を捉える観察に基づく仮説思考
- 3.表現力
-
理解を客観的な言語や視覚化(相づちなどの身体反応)により表現することで、他者との意思疎通が容易になり、思い込みも補正しやすくなる
周りの機微を察する敏感なセンサーによる状況認識、その状況をより深く理解し自分事化するための情動的な感情移入、そして、理解を俯瞰するために言語化・視覚化などに成形し客観的に情報を整理することで、他との繋がりが構築され共感することができるようになります。
共感力が求められる職業には、介護の現場や看護、さらに商品開発からサービス業、また、演劇や映画の役者なども挙げられます。これらに共通する特徴として、観察力、想像力、表現力を駆使することが求められます。
共感力が特に求められる職業として、演劇や映画の役者などが挙げられます。役柄に同調して、現実感を生み出すために観察力から学び得る情報、理解を補うための想像力、そしてその理解を演じる表現力で構成していると言えます。
なお、私たちがこのような共感力を身につける手軽な方法として、読書や映画・演劇を鑑賞するなど、観察や想像力なども鍛える有用な方法として有名です。
特に読了や鑑賞後に他者と感想の意見交換をすることで、多様な視点に触れることもでき、客観性を養い共感する下地を整えることも期待できます。
※以下の関連ページで、共感力を高めるエクササイズを紹介しています。
デザイン思考の成功に重要な「共感」と「同情」の違いを解説
はじめにも触れましたが、同情とは初動の感情移入で、そのままでは問題の本質に届かないことがあります。あくまで客観的な視点を要しながら問題の表層と深層も捉えることで課題設定に繋げていくことがデザイン思考における「共感」の目的であり、感情に同調するだけの「同情」との大きな違いと言えます。
感情を捉えた後、その根源を深く追求し、最適な問題定義へ導くことが重要です。それにより、思い込みによる短絡的な結論に結びつけを回避することが重要になります。
まとめ
ユーザーエクスペリエンスにおける「共感」を整えるために
ユーザーエクスペリエンス設計において、対象者の潜在的ニーズを浮かび上がらせるための理解フェーズの共感行為は客観的に対象者を理解することで対処すべき課題の精査が可能になります。
「にじり口」のような空間的仕掛けの活用方法として、例えばワークショップを開催する場合などは、職場と異なる空間であえて開催し、個人のPCやスマートフォンは排除して、私服で参加することを敢えて推奨します。
新たなアイデアを発見し合う時に、このような非日常の演出は、心持ちを整える千利休が意図的に仕掛けた「にじり口」のような仕組みに繋がります。
今後はユーザーエクスペリエンス(UX)を実施するための、洞察を深める観察方法や心構え(=マインドセット)、ツールであるペルソナ設定やジャーニーマップなどの利用法なども「UXの茶釜」などで紹介していきます。
- 対象者の深層的課題を理解するためには客観的視点が重要
- 共感/理解を妨げる3つの要因:「無関心」、「自己中心」、「偏見の眼差し」
- 共感構造の3要素:「広い視野の観察力」、「観察に基づく想像力」、「表現を駆使してアイデアを補正し共有」
- 同情との違いは、対象者へ感情移入を行いながらも客観的な視点で課題の深層を発見する目的とする点
- アイデアを出し合う時などは、非日常の演出「にじり口」的な仕掛けで気持ちをリセットする
参考文献:
- ペン編集部「千利休の功罪。 (Pen BOOKS) 」 CCCメディアハウス 2009年
X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事の読み逃すことなく閲覧できます。