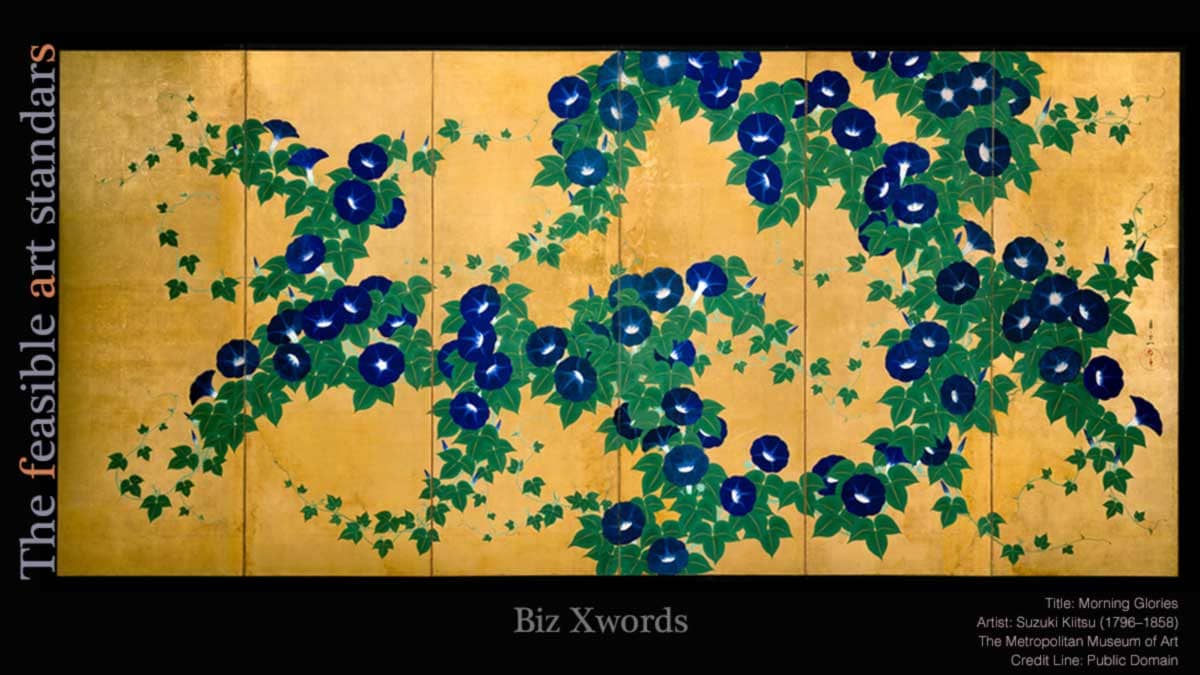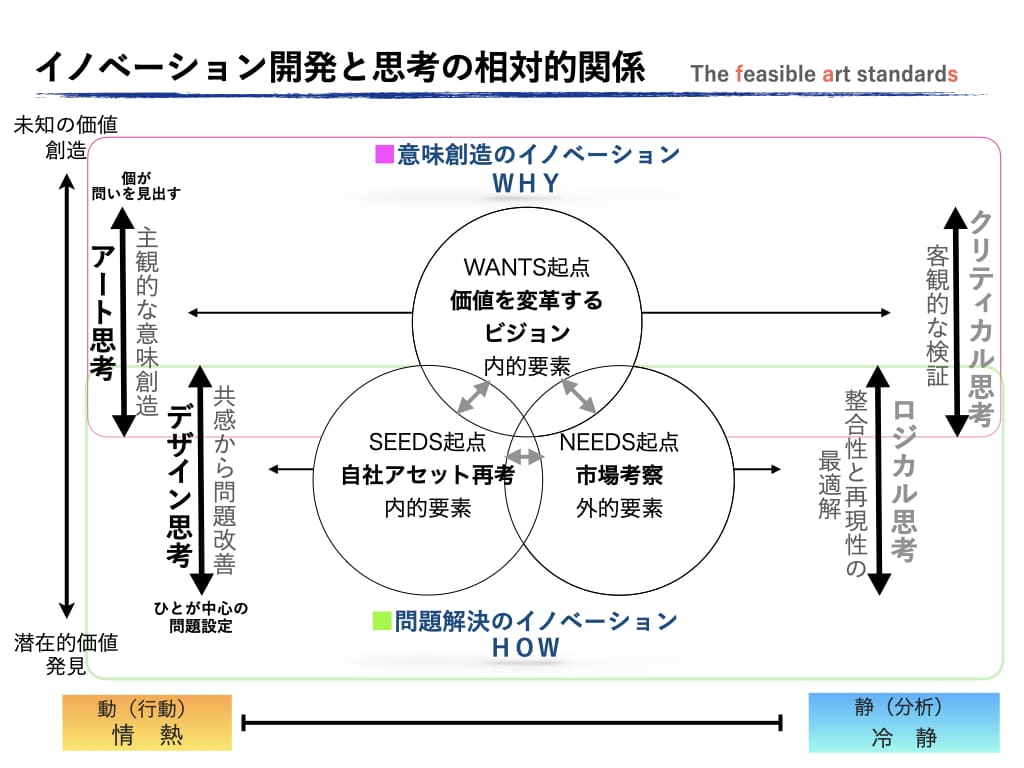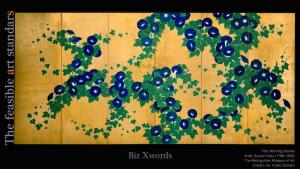『なぜうちの会社は、差別化できないのか?』
多くの経営者が抱えるこの悩みに対し、コンビニ業界のローソンが示す解決策は明快です。業界3位でありながらブランド価値1位を獲得したローソンの戦略は、企業規模に関係なく応用可能な普遍的な原理に基づいています。
本記事では、シュンペーターの5つのイノベーション分類を通じて、ローソンの差別化戦略の本質を解明し、あなたの事業で今すぐ実践できる具体的な手法を提示します。
新規事業や斬新な事業展開の企業事例を紹介するビジネス クロスワード:ビズクロ企画。第一回は、進化し続けるコンビニ業界におけるローソンの経営戦略における差別化のケーススタディを考察します。
キーワードは、「多角化経営とハイブリッド・イノベーションの実践」です。
コンビニ業界の飽和市場時代と差別化戦略
業界現状とローソンの差別化戦略への挑戦
米国発祥の小型店舗の小売チェーン展開が日本国内ではじめて開業したのは、1974年のセブン・イレブンが東京都江東区豊洲の1号店でした。それ以来、飲食料品の販売を中心に日用品の小売りから、ATMやマルチ通信端末設置、金融や各種支払手続きの代行業務など生活全般をカバーする業態へ独自の進化を遂げてきました。
その後、都市ではコンビニが乱立する商圏制覇の飽和状況や、人手不足による深夜営業を抑える業務の変更も現れてきました。
また、値引き販売が無い点では、製品メーカーにとってはコンビニで商材を取り扱ってもらうメリットがあります。そこで、コンビニと共同でプライベートブランド商品の開発やキャンペーンも盛んに行われ差別化も行われて来ました。
現在では、大手3社であるセブンイレブン、ファミリマート、ローソンでは、自社オリジナル惣菜やスイーツなど商品開発をメインの差別化要因としつつも、地域の便利な小売店から新しい切り口の事業展開(=イノベーション)が模索されています。
次項では、独自の店舗展開や事業成長を続けるローソンの成長戦略をイノベーション観点の事例を交えて紹介します。
ローソンの差別化戦略|ハイブリッド・イノベーション
多角化経営で差をつけろ
ナチュラルローソン・未来型書店など実例
セブンイレブン、ファミリーマートに続くコンビニ市場シェア業界3位のローソンは、業界で初となる試みや異業種との積極的な協業などで差別化を施してきました。
日経BPコンサルティングの2024年11月に実施したブランド価値調査「ブランド・ジャパン2025」の一般生活者編では、コンビニエンスストアのブランド価値ランキングでは競合を抑えて堂々の1位になりました。
ローソンの沿革(抜粋)
| 年表 | ローソンの動き |
|---|---|
| 1977年11月 | 業界初の物流センター設置 |
| 1996年3月 | コンビニ初、切手・はがき・収入印紙取り扱い開始 |
| 1997年11月 | コンビニで初めて天然ガス使用の低公害配送車の導入 |
| 2006年9月 | 民間企業初、環境省と「環境保全に向けた自主協定」を締結 |
| 2014年5月 | フィットネスジム運営、株式会社ルネサンスと、健康寿命の延伸を目指して「健康に関する業務提携」を締結 |
| 2014年10月 | 複合書店フタバ図書とコンビニエンス ストアが一体となった「未来型書店コンビニ」オープン |
| 2015年4月 | 埼玉県川口市にシニアとご家族を支援するケア(介護)拠点併設型店舗1号店をオープン |
| 2016年12月 | 業界初の完全自動セルフレジ機「レジロボ®」とRFID(電子タグ)の実証実験開始 |
| 2018年8月 | 調剤薬局併設の「ローソン千駄木不忍通」店が薬・介護・栄養相談ができる店舗としてリニューアルオープン |
| 2021年2月 | Uber Eatsでは国内初となる医薬品のお届けを開始 |
| 2021年6月 | 「LAWSONマチの本屋さん」を立ち上げ |
「マルチフォーマット戦略」とは?ローソン独自の店舗展開モデル
ローソンの企業理念は、地域社会と人々への配慮を重視し、『健康志向』と『環境保全』を掲げています。もちろん、競合他社も利便性だけでなく環境問題、健康を意識した企業理念を掲げています。
しかし、他社ではワンフォーマットと呼ばれる同一型の店舗サービスの提供を展開する一方、ローソンは『マルチフォーマット戦略』で多様な店舗形態を展開してきました。
具体例では、ナチュラルローソンやローソン100、ヘルスケアローソンや院内店舗のホスピタルローソン、また、書店型コンビニなど、通常店舗と異なる店舗形態や異業種との提携による集積型の多角化*(コングロマリット)ビジネスモデルです。*既存分野で垂直統合や水平統合など広義の多角化に対し、異なる分野の新市場でビジネスを展開する集積型(コングロマリット)ビジネスモデル。
※タイトルをクリックすると記事が現れます。
【コラム】イノベーション理論の概要
19世紀オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーターが唱えた「経済発展の理論」の概念は、技術革新だけではなく技術の応用による製品開発や生産方式の改良、新たな供給源の確保、また、新たな組織の創出や販路開拓、独自の市場開発など新しい組み合わせによる革新となる「新結合」という表現が用いられ、後に、イノベーションという表現が補足されました。
- プロダクト・イノベーション:新しい財貨(=価値)の生産
- プロセス・イノベーション:新しい生産方法や商業的な取扱方法の導入
- マーケット・イノベーション:新たな販路の開拓
- サプライチェーン・イノベーション:原材料の新しい供給源の獲得
- オーガニゼーション・イノベーション:新しい組織の創出
次項では、各イノベーション施策から事業成長における具体的なローソン施策の事例をみていきます。
シュンペーター理論のコンビニ応用事例
ローソンのイノベーション5類型
- プロダクト・イノベーション:新しい財貨(=価値)の生産
- プロセス・イノベーション:新しい生産方法や商業的な取扱方法の導入
- マーケット・イノベーション:新たな販路の開拓
- サプライチェーン・イノベーション:原材料の新しい供給源の獲得
- オーガニゼーション・イノベーション:新しい組織の創出
2020年のコロナ禍で、竹増社長は店舗の在り方の基本デザインを見直すために「大変革実行委員会」を社内に立ち上げ、商品、売り場作り、マーケティング、ブランディングなど12分野ごとに検討会を設けて検討をつづけ店舗経営の見直しを実践していきます。
「プロダクト・イノベーション」で魅せる、日常生活にもっと身近な存在へ
新しい財貨、すなわち消費者の間でまだ知られていない財貨(=価値)、あるいは新しい品質の財貨の生産
シュンペーター『経済発展の理論』原書第2版、塩野谷祐一、中山伊知郎、東畑精一訳、岩波文庫、1977
「まちかど厨房」と「盛りすぎチャレンジ」事例
2022年から本格展開した「無印良品」の商品導入や、店舗で温めるチルド弁当から炊きたてのご飯が食べられる「まちかど厨房」の立ち上げにより、コロナ禍での購買率を支えました。
2023年2月には、単に値引きで一過性の購買促進を進めるだけでなく、生活者にインパクトを残し長期的な印象を残す期間限定のシリーズ企画として、「盛り過ぎチャレンジ」で商品内容量を47%増量したお得感と驚きを提供する商品開発などをヒットさせました。
そもそも、2021年にファミリーマートが、開始したサンドイッチや惣菜の「40%増量作成」企画が先行キャンペーンとして開催されていました。後発のローソン側の企画では、商品の見せ方や楽しさを「チャレンジ」という表現でSNSでの拡散を後押しする点が功をなしたと考えます。
「プロセス・イノベーション」で効率化
新しい生産方法、すなわち当該産業部門において実際上未知な生産方法の導入。これはけっして科学的に新しい発見に基づく必要はなく、また商品の商業的取扱いに関する新しい方法をも含んでいる。
シュンペーター『経済発展の理論』原書第2版、塩野谷祐一、中山伊知郎、東畑精一訳、岩波文庫、1977
「まちかど厨房」など生産プロセス/物流の改革
ローソンでは、店内で手作りのおにぎりやお弁当を作る「まちかど厨房」のキッチン設備を設けることで、廃棄ロスや物流負荷の軽減を行っています。
その効果は、物流が困難な遠隔地や豪雪地域でも倉庫スペースを拡充し冷凍食材で店内調理を行い、作りたて調理品を提供出来るようにしました。これにより、頻繁な物流が困難な離島である佐渡島や北海道の最北端の稚内など競合他社が敬遠しがちな地域にも出店してきました。
ナチュラルローソン「茗荷谷駅前店」(東京都文京区)では、2025年7月8日からテストマーケティングとしてサラダを店内の対面販売で9種類のトッピングを選んでカスタマイズできる『できたてBOWL SALAD』(864円税込~)を販売開始しました。

「できたて」「カスタマイズ可能」という一般的なコンビニ商品企画とはことなるコンセプトを打ち出します。まさに新たな企画力で、買い手も売り手も、そして、地域社会にも良い影響を与える「三方よし」の発想を実現しています。
またローソン本体では、商品の扱いも店頭販売のみならずKDDIと提携しEC販売も行うにあたり、販売拠点である店舗を物流倉庫として捉えて全国47都道府県の約1万4500店舗を活用して注文から最速で15分で配達できるデリバリーネットワークを構築しました。
その分、店舗側のオペレーション負荷を見越したセルフレジの導入やスマートフォンで商品をスキャンし決済を完了するスマートフォンレジなどデジタル技術を積極的に取り入れ業務内容の改善にも取り組んでいます。
さらに、今後は薬剤師などの専門資格者の対面販売に限られている一般医薬品をオンラインによるリモート問診を導入することで24時間、購入や配達が出来るように厚生労働省と計画を進めています。
まさに、あらたな生産方法の導入のみならず商習慣の改革において新たな方法を見出すプロセスイノベーションを実践している好例と言えます。
「マーケット・イノベーション」で売上20倍
新しい販路の開拓、すなわち当該国の当該産業部門が従来参加していなかった市場の開拓。ただしこの市場が既存のものであるかどうかは問わない。
シュンペーター『経済発展の理論』原書第2版、塩野谷祐一、中山伊知郎、東畑精一訳、岩波文庫、1977
地域課題に根ざす新市場の開拓
日本RV協会などと提携し、千葉県のローソン6店舗の駐車場で車中泊施設「RVパーク」の実証実験を開始しました(2025年7月14日)。国内の宿泊費の高騰を背景に、車中泊の需要が高まっていることや駐車場の有効活用にもつながることから実証実験に踏み切りました。

車中泊施設「RVパーク」実証実… コンビニエンスストア「ローソン」の公式ウェブサイト。店舗/ATM検索、新商品紹介、各種店舗でのサービスや活用方法などのご紹介。株式会社ローソンの企業情報掲載。ローソ…
地域課題を「ついで買い」などの購買心理で探索
電子書籍やEC販売が主流となる中、街から本屋の姿が消えて、24時間、いつでも書籍や雑誌を手に取れる書店併設型ローソンを2014年から出店しました。
その背景には、書店が一つもない市区町村は全国で26.2%も存在する現状でした。そこで、ローソンは自治体や地域の書店とコラボレーションを図り書店併設型のコンビニ店舗を出店しました。
2021年からは、日本出版販売株式会社と連携してローソン独自の書店併設型店舗「LAWSONマチの本屋さん」を開業しました。
その結果、書籍・雑誌カテゴリーの合計売上が全国のローソンの平均と比較して約20倍となる店舗も出て来ました。
本来、コンビニの雑誌などの販売は隙間時間を埋める働きでお弁当や飲料との「ついで買い」として相性のよい商品でした。
またリアルな書店の場合、手に取り意図せぬ好奇心との出会いはデジタル空間の推薦機能より興味を揺さぶられることがあります。
特に深夜のコンビニでは、時間を気にせずに物色しながら衝動的な「ついで買い」の行動変容が起こりやすいと推測され、この2つの「新結合」が購買動機のみならず来店動機の形成にも繋がると考えます。
さらに、少子化高齢社会における地域課題を見据えた介護の拠点窓口となるケアローソンや薬局を併設したヘルスケアローソンなどの新業態の店舗にも取り組んでいます。
「オーガニゼーション・イノベーション」でヒット商品を紡ぐ
新しい組織の実現、すなわち独占的地位(たとえばトラスト化による)の形成あるいは独占の打破。
シュンペーター『経済発展の理論』原書第2版、塩野谷祐一、中山伊知郎、東畑精一訳、岩波文庫、1977
コンビニにおいて、自社の商品開発は売上げに影響を与える生命線であり、その中でもおにぎりに続いてスイーツ類は主力ラインナップです。
ローソンは、2009年9月にコンビニスイーツのブーム火付け役となった「プレミアムロールケーキ」発売以来、数々のスイーツのアイデアを編み出してきました。
2019年3月には、「バスチー:バスク風チーズケーキ」を投入し世間でも新たなブームを巻き起こしました。その製品開発においては、従来と異なる稟議システムを組織内に導入し、企画開発のマーチャンダイザー(MD)の現場の声を直接聞く組織構造の改革が行われました。
現場主義から商機の兆しを育む企業文化
一般的な大企業では、物事の承認申請において最終決済者の説明までには、何人もの中間チェックが行われます。それ故に、オリジナルのアイデアは補正が施され、幹部社員の嗜好性を忖度するあまり無難で従来通りな企業カラーにアイデアが落ち着く傾向がありました。
現場の直接的な意見を聞き斬新なアイデアを編み出すために、そして商品の導入を素早く実現するために竹増社長が組織構造を変革しヒット商品のサイクルを紡いでいきました。
おわりに
ローソン戦略の未来予測・展望
コンビニ業界は、前述したように出店数など国内は飽和状態となり、ビジネスモデルもフランチャイズ方式という業態で斬新な差別化が付けずらい飽和状態の業界でした。
ローソンの経営戦略には、2030年代のビジネス環境変化を見据えた以下の先見性があります;
今後10年の事業環境予測
- 少子高齢化加速による地域インフラ需要の変化
- AI・IoT技術の普及による無人化・自動化の進展
- サステナビリティ要求の高まり
- パーソナライゼーション需要の拡大
ローソン戦略の将来的優位性:
- 地域密着型事業展開: 人口減少地域でのライフライン機能
- テクノロジー活用基盤: 既存のデジタル投資が競争優位の源泉
- 社会課題解決型ビジネス: ESG投資拡大トレンドとの親和性
- 柔軟な組織構造: 変化対応力が持続的成長の鍵
業界横断的な経営戦略の応用
ローソンの差別化戦略から導き出される普遍的な成功法則は、コンビニ業界に留まらず、あらゆる成熟産業で応用可能です。
他企業への示唆:
- 短期的な収益性より、長期的な社会価値創造を重視
- 既存事業の延長線上ではなく、異業種との「新結合」を積極追求
- 組織の硬直化を防ぐ継続的な構造改革の重要性」
製造業への応用例:
- 「まちかど厨房」→工場内での小ロット生産による在庫削減
- 「マルチフォーマット戦略」→顧客セグメント別の製品ライン展開
- 「現場主義の組織改革」→製造現場の声を直接経営陣に届ける仕組み
サービス業への応用例:
- 「書店併設型店舗」→異業種コラボレーションによる新市場開拓
- 「デジタル×リアル融合」→オンライン・オフライン統合サービス
- 「地域課題解決型事業」→社会性とビジネス性の両立
中小企業での実践ポイント:
- 限られた資源でも「一点突破」の差別化は可能
- 顧客との距離が近い中小企業こそ「現場主義」が活かせる
- 大企業が参入しにくいニッチ市場での「新結合」を狙う」
独自の物流網の構築や異業種との協業によるサービス拡充、そして、一般的なコンビニ業界とは異なるマルチフォーマット業態の独自の展開により業界内のポジションを確立してきました。
それらは企業理念に基づいた行動により、小売業の枠を超えた地域との信頼構築や安心や安全なサービスの提供に発展させた事業展開は謙虚でありながら自信の現れとも言えます。
中小企業にも効く!ローソン戦略から学ぶアクションプラン
最後に、ローソンの成功事例を自社で実践するための具体的ステップを提示します。
フェーズ1:現状分析と機会発見(1-3ヶ月)
- 自社の競争環境における「飽和度」の客観的評価
- 顧客の潜在ニーズと競合の空白地帯の特定
- 社内リソースの棚卸しと「新結合」の可能性探索
フェーズ2:小規模実験の実施(3-6ヶ月)
- ローソンの「まちかど厨房」に学ぶ小規模なテスト店舗の設置
- 異業種パートナーとの協業のテスト実施
- 現場社員の意見を直接経営陣に伝える組織の仕組み構築
フェーズ3:本格展開と組織改革(6-12ヶ月)
- 成功したテスト事例の水平展開
- 「変革実行委員会」型の組織構造改革
- デジタル技術を活用したプロセス改善の実装
成功確率を高める3つの留意点:
- 企業理念との整合性を常に確認
- 短期的な失敗を許容する組織風土の醸成
- 競合他社の動向ではなく、顧客価値創造に集中
測定するKPI:
- 新規事業からの売上構成比
- 顧客満足度・ブランド価値の向上
- 組織の意思決定スピードの改善モニタリング
事業構想における着眼点とポイント:
- 多様なイノベーション手法の複合的活用
- 地域特性に応じた柔軟な経営展開
- 現場主導の意思決定とその実現のためのアジャイル組織改革
- 社会課題解決から導く事業成長の礎
- デジタルとリアルを融合させる経営視点の実施
- 他社との協業による「新結合」で市場を掘り起こし提供価値を確立し続ける
- DXなどテックのちからを活用して社会課題の解決を地域や自治体、国をも巻き込んで推し進める
- 生産プロセスの見直しや新たな商品の取り扱い方法の発想で既存資産を物流網に変換するなど視点の変換を活用
- 現場主義を経営に活かすためにトップが直接的に現場の声を聞き入れる組織作り
- 企業理念のブレない形で事業成長を進める意志と決意
参考文献
- J.A.シュンペーター「経済発展の理論上・下」日岩波書店 1977年
- ローソンHP>企業情報:2024年6月19日閲覧
- LAWSON RECRUIT SITE 「コンビニ業界とローソン」:2024年6月19日閲覧
- ローソンIR情報>統合報告書2023 (PDF :6.73MB):2024年6月21日閲覧
- BUSINESS INSIDER 「1分でわかるコンビニ3社決算」:2024年6月21日閲覧
- YouTube日曜日の初耳学チャネル「46歳でローソンの社長に!カリスマ社長の仕事術」:2024年6月2日閲覧
- 日経ビジネス「ローソン竹増社長「笑えるほどのお得感で単なる値引きよりワクワク」」:2025年4月16日閲覧
X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。