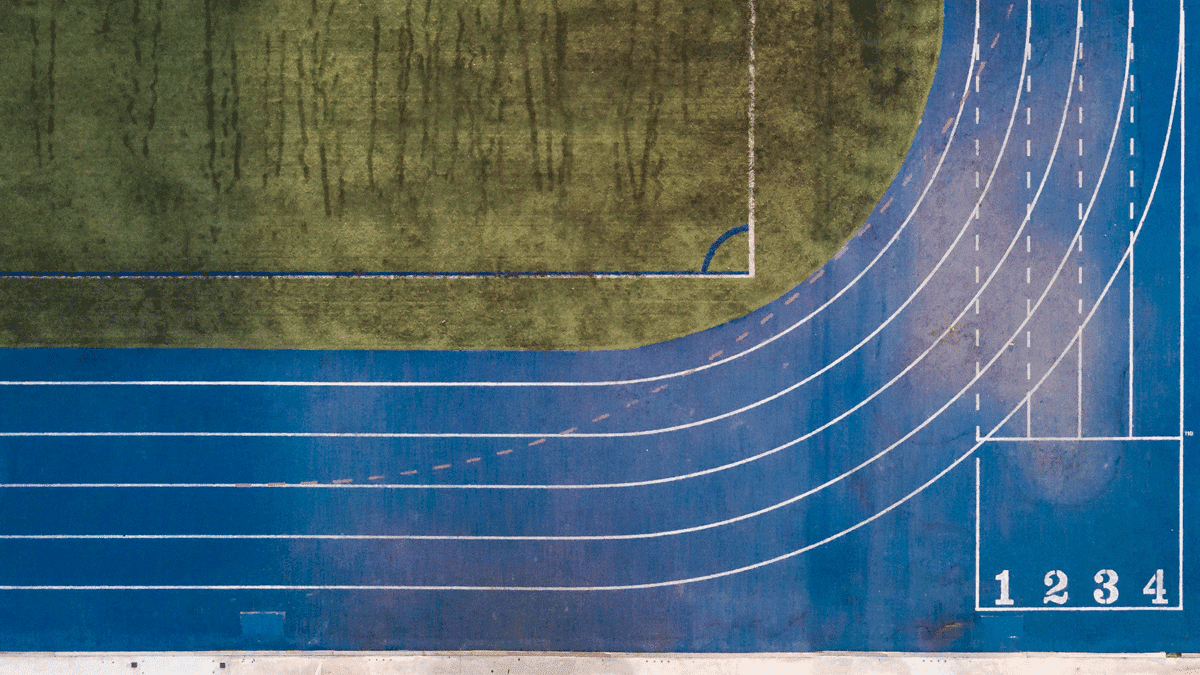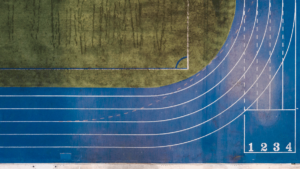サービスデザインとは、消費者の価値観が「モノ」から「コト」へと移行する現代において、顧客に対して一貫性のある体験価値を設計し、構築し、継続的に提供するための体系的な方法論です。ここでの「サービス」とは、単なる対人サービス(例:ホテル業・接客業)に限定されず、顧客が商品や企業との関わりの中で得るすべての体験や感情を含みます。
つまり、製品の機能だけでなく、購入前後の接点や感情の流れまでを含めた「体験全体」がサービスの対象となるのです。有形商品であっても、無形サービスであっても、それらが提供する総合的な価値を包括的にとらえるのがサービスデザインの本質です。
本記事では、このサービスデザインの基本的な考え方と、その背後にある本質的な価値について、実例とともにわかりやすく解説していきます。
サービスデザインが求められ背景と価値の変遷
情報流通の逆流現象と「モノ」から「コト」へ価値変容
1990年代後半、生活者と企業の関係性は大きく変化し始めました。企業から生活者への一方通行だった情報発信の流れが逆転し、生活者自身が情報の発信源となり始めたのです。物流の進歩により地理的な制約が解消され、モノは世界中のどこからでも迅速に入手可能となりました。
同時にインターネット環境の普及により、ブログやSNSなどを通じた個人による情報発信も始まりました。これにより、必要な情報の入手経路が増加し、一方的に押し付けられた情報ではなく、自ら情報の真意を確認することが可能となりました。
単に機能が優れた「モノ」そのものの所有欲から、個人のこだわりや価値観を満たす「時間」や「体験」へと、価値の焦点が移行していきました。このような満足の源泉は、モノにまつわる一連の体験、すなわち「コト」として認識されるようになったのです。である「コト」を指してきました。
サービスデザインの領域
時間と空間を交差する総合的な価値
サービスデザインを「旅行」に例えるなら、現地滞在だけでなく、出発前の計画から帰宅後の余韻に至るまで、一連の体験全体が「旅の本質的な価値」といえます。同様に、ユーザーにとって意味ある時間の流れ全体を包括的に設計することが、総合的なサービスデザインの要点です。
また、その時間軸の中で、オンラインや現実の世界(店舗、問合せ対応、広告など)におけるあらゆる接点の空間軸において変わらない顧客満足を提供することが重要になります。
実際にサービスモデルを設計、改善するためのツールを活用する時にも、基本、この時間軸と空間軸を意識する事で統一
リピートを生み出す循環型「ビジネスサイクル」
自社のサービスや商品を再び利用してもらうために、継続したコミュニケーションの仕組みが必要になります。コミュニティを形成したり、メルマガなどで定期的な対話の接点を設けるのも定石ではあります。
サービスデザインにおいては、顧客体験を定期的に見直し・改善することを通じて、ユーザーの体験をシームレスかつ循環的に設計する意識が求められます。
それにより、継続した顧客との関係が築かれていきます。つまり、ビジネスデザインの本質を簡易的に表現すれば、「ユーザー中心のビジネスモデルの最適化」です。
サービスデザインの6要素
ここで、参考までに経産省で掲載されているサービスデザインの6要素を紹介します。
6つの要素から成るサービスデザインの構成
- 1. 人間中心
-
サービスの影響を受けるすべての人のエクスペリエンスを考慮する
- 2. 共働的であること
-
サービスデザインのプロセスには多様な背景や役割を持つステークホルダーが積極的に関与しなければならない
- 3. 反復的であること
-
サービスデザインは、実装に向けた探索、改善、実験の反復的アプローチである
- 4. 連続的であること
-
サービスは相互に関連する行動の連続として可視化され、統合されなければならない
- 5. リアルであること
-
現実にあるニーズを調査し、現実に根差したアイデアのプロトタイプを作り、形のない価 値は物理的またはデジタル的実体を持つものとしてその存在を明らかにする必要がある
- 6. ホリスティック(全体的)な視点
-
サービスはサービス全体、企業全体のすべてのステークホルダーのニーズに持続的に対応するものでなければならない。
出典:経済産業省「我が国におけるサービスデザインの効果的な導⼊及び実践の在り⽅に関する調査研究報告書[詳細版]」(PDF: 55.8MB)
上記のポイントに理解を深めるための補足を記述していきます。
1,2.「人間中心」、「共創的」について
ここで想定する「人間中心」の対象は、製品やサービスの利用者だけでなく、企業内部の関係者や従業員も含めたすべての「人」です。
特に2.「共創」においては、「すべてのステークホルダー(利害関係者)」が協働の対象となり、顧客のみならず、部門を越えた従業員同士の連携も含まれます。
優れたサービスモデルは、提供者である従業員が誇りと自信を持ち、そのポジティブな感情が、顧客にとっての満足体験へとつながっていきます。
例として、ディズニーランドのキャスト、スターバックスのバリスタ、または、アップルストアーのスタッフなどが挙げられます。
3.「反復的であること」
これは、「デザイン思考」などでも共通するアイデアを形にする考え方(=マインドセット)で、より深い洞察に近づくための手段です。繰り返し考え抜くことで、余分な固定概念や思い込みを削ぎ落としていきます。
4.「連続的であること」
これは先述した旅の例のように、サービスを1つの点で捉えるのでなく大きな時間の流れ(=時間軸)で見据えることになります。
5.リアルであること
ここで言う「リアル」を別の言葉で表現すれば、「実感する」という意味に置き換えられます。例えば小売業界などは、対面販売からネット通販へ売り上げ比重も移行してる中で、返品ポリシーが店舗販売とネット通販で異なる場合、顧客側からすれば納得のいく購買体験の実感は持ち辛いでしょう。
また無形のサービス(もしくはコンセプト)の場合でも、可視化した手順を示すビジュアル・サービスマップを作り、実際に図式化して確認することで見落としや思い込みなどの誤解の排除に有効と考えられます。
この目視による「実感=現実の確認」という物理的な行為が「リアル」の言葉には内包されています。それは、アイデアを机上の理論で終わらせないための姿勢でもあります。
デザイン思考との関係性
以前の記事:「「デザイン思考」の考え抜く技術」で述べたデザイン思考のポイントでは、適切な課題の発見と解決策を見出すプロセスが重要と話しました。サービスデザインは、ビジネスに実際にこの概念を実践するための総合的なアプローチと考えます。
スポーツに例えるなら、デザイン思考は選手個々のスキルや能力を高める「個別強化」の役割を担い、一方でサービスデザインは、試合におけるフォーメーションや戦術など「チーム全体の最適化」を図る総合戦略に該当します。
つまり、サービスデザインは、デザイン思考を構成要素として組み込みながら、ビジネス全体を包括的に設計・最適化するための「戦略的な手順書(プレイブック)」と捉えることができます。
まとめ
サービスとは、有形の「モノ」だけでなく、ユーザーが体験する感情や行動、時間の流れを含む「コト」までを含めた総合的な価値です。
その範囲は、時間軸(準備・利用・振り返り)と空間軸(店舗・オンライン・広告など)の2軸で捉えることで、ユーザーにとって意味のある体験が設計できます。サービスの構築と継続的な改善には、顧客・従業員・経営層など、すべてのステークホルダーとの協働が欠かせません。
そして、デザイン思考を基盤に据えたサービスデザインは、個別の施策をつなぎ、ビジネス全体の価値を最適化するための「実践的プレイブック」として機能します。
これからのビジネスにおいて、「体験をどう設計するか」は競争力そのものです。読者の皆様が、サービスデザインの本質を正しく理解し、自社の戦略にどう活かすかを考える第一歩となれば幸いです。
- サービスとは、モノだけでなくユーザーが感じる感情やあらゆる一連の体験を含む
- その範囲は、時間軸と空間軸の2軸で考える
- サービスの構築と提供において、関わるすべての利害関係者の協力を要する
- デザイン思考を利用し、実際にビジネスの全体最適化を実施するための手順書(=プレイブック)
X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。